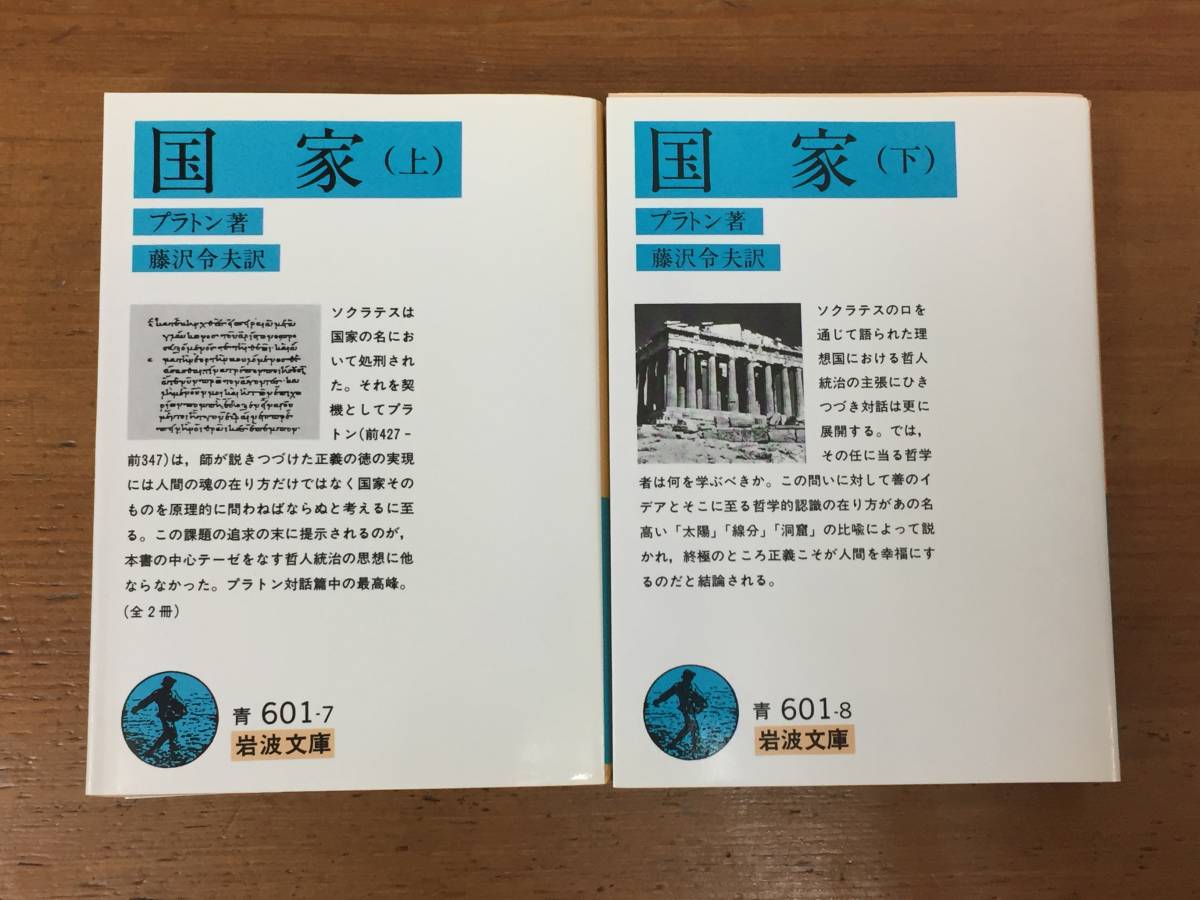
長年に渡り世界中で読み継がれている哲学や倫理学、心理学の名作をまとめました。古代ギリシアの哲学者プラトンの『国家』や、ドイツの思想家ニーチェの『道徳の系譜』など、各作品の基本情報や読者の感想をまとめています。哲学入門編にぴったりな本もまとめて紹介しています。
科学技術の拡大により、間違いなく世界は小さくなっています。そのため従来の倫理規範では対応できない問題がたくさん現れてきました。このハンス・ヨナスの著書だけがもちろんすべてではないし、すんなりと受け入れられない点もあるかと思います。しかし、彼の生涯をかけたこの一冊には何か鬼気迫るものがあり、圧倒されてしまいます。
出典: www.amazon.co.jp
とある事情のため非常に読みづらいドイツ語で書かれているのですが、翻訳者の努力のためわかり易い簡潔な日本語で読むことが出来ます。環境問題や医療に関心がある人はもちろん、広く一般の方に手に取って頂きたいです。
出典: www.amazon.co.jp
我々は否応なく現代人として生きていかねばならない。一見当たり前のようなことが、私たちの肩にのしかかってくる。未来の世代を簡単に壊してしまうことすらできてしまう現代の私たちの科学技術力を、私たちはどう考えるべきか、環境問題を考える上で非常に重要な一冊。
出典: www.amazon.co.jp
ヨナス『責任という原理』読了。全く共感できないぶん、こんな意見もあるのかと思って興味深かった。原語では難文のようだが、同一メッセージのパラフレーズが続くし訳も分かりやすいので、この手の本としてはすこぶる読みやすいのでは。にしても、ここまでブロッホ批判に徹してるとは思わなかった。
— 荒木優太 (@arishima_takeo) August 7, 2016
勉強会なので、ヨナス『責任という原理』読み返してる.「必要性が強いる日々の強制は、不正を被っているという感情さえ押しつぶしてしまう」というのは、本当に今日的な問題だな.
— Rei (@uhlnebv) December 7, 2013
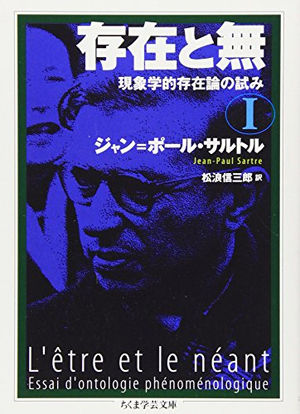
出典: www.amazon.co.jp
サルトル『存在と無』
人間の意識の在り方(実存)を精緻に分析し、存在と無の弁証法を問い究めた、サルトルの哲学的主著。
根源的な選択を見出すための実存的精神分析、人間の絶対的自由の提唱など、世界に与えた影響は計り知れない。
フッサールの現象学的方法とハイデッガーの現存在分析のアプローチに依りながら、ヘーゲルの「即自」と「対自」を、事物の存在と意識の存在と解釈し、実存を捉える。
20世紀フランス哲学の古典として、また、さまざまな現代思想の源流とも位置づけられる不朽の名著。
1巻は、「即自」と「対自」が峻別される緒論から、「対自」としての意識の基本的在り方が論じられる第二部までを収録。
高校生の時、読み始めたサルトルの著作は、衝撃であり魅力的であった。
読み進むにつれ、眼の前の世界が音を立てて崩壊し、新しい世界が立ち現れてくるような、強烈な感覚に襲われた記憶がある。
出典: www.amazon.co.jp
中でも「存在と無」は難解を極めたが、意識(つまりは僕自身に他ならない)について、あらゆる角度から根源的に定義付けているために、これを理解することができなければ、この先まともな人生を送ることは不可能ではあるまいか、と勇ましくも真面目に思い悩んだものであった。
出典: www.amazon.co.jp
なんとか理解できたと思った時は、周りの人間達が、教師も含め大人全員がどうしようも無い俗物どもに見えてきた。
サルトルの毒は、劇薬であった。
以来、社会に出てからも「存在と無」で展開された世界観を引きづりながら、間接的ではあるが、長期に渡って束縛されたのである。
出典: www.amazon.co.jp
サルトル:人間はあらかじめ本質や定義を与えられている存在ではなく、自由な存在であり、自己を社会に投企し(投げ込み)、社会を変化させていくといった社会参加(アンガージュマン)をとおして自己および社会の自由を実現していく、と説く。主著『嘔吐』、『存在と無』、『弁証法的理性批判』
— 哲学ボット (@tetsugakubot) April 24, 2017
サルトル、「嘔吐」はすげー眠くなるけど「存在と無」は眠くならない
— chû (@chu_fuzimura) May 28, 2017

出典: www.amazon.co.jp
ベルグソン『時間と自由』
ベルクソンの哲学的出発を告げた時間論の古典的名著。
「意識に直接与えられた」現実を純粋な時間的持続とみなす立場から、自由の決定論と非決定論の双方を“時間の空間化”として批判した。
時間意識の緻密な分析を通して具体的現実の復権と真の自由の顕彰を図った20世紀初頭の思想動向を代表する記念碑的労作である。新訳。
哲学でノーベル文学賞を受賞したのはベルクソンとラッセルだけです。サルトルは辞退しました。20世紀初頭の思想動向を代表する記念碑的労作です。
出典: www.amazon.co.jp
フランスの哲学者ベルクソン(1859〜1941年)が1888年にソルボンヌ大学に学位論文として提出した著作。原題は『意識に直接与えられたものについての試論』。
本書の主題は、序言に「多くの問題のうちから私たちは形而上学と心理学とに共通の問題、すなわち自由の問題を選んだ」と書かれている通り、「自由」、そして「時間」である。
出典: www.amazon.co.jp
カントの空間と時間の思想を受けて、時間は空間とは別な特徴を持っていることを論じている。
さらに、決定論と自由論について論じ、双方の問題点を論じている。
哲学の伝統的なテーマである、空間と時間、決定論と自由論について、
新たな視点で、独自の見解を披露する、ベルクソンのセンスはさすが。
その一方で、本来自由になれるべき人間が、慣習などに流されて、自由を発揮せず、
漫然と行動していることを批判もしている。
出典: www.amazon.co.jp
ベルグソンの自由と時間を読む時間が欲しい
— 宮野 岳 (@miyanotakesi) November 9, 2014
僕がクラシックと言われる音楽をやって、やめて、今度はテクノと呼ばれるジャンルに傾倒して、その中で、ピアノや、テクノではシンセとかアシッドラインといったものに関して一貫して考え続けていたことが、ベルグソン「時間と自由」の中の、たった数行に集約されていた。
— Pさん (@pyidesu) February 11, 2014
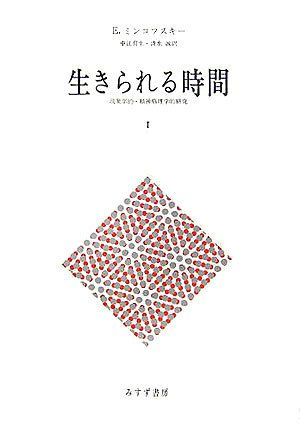
出典: www.amazon.co.jp
ミンコフスキー『生きられる時間』
本書はミンコフスキーの代表的な著書として、また時間論の名著として、長い間、その翻訳を待たれていたものである。
1927年に『精神分裂病』を著わした著者は、分裂病者の時間と空間における特殊な存在の形態、特異な世界への入口を模索しつづけていた。ベルクソン、フッサールの影響が色濃く影を落している本書はその延長線上にある。
1993年、『生きられる時間』が生れたときは、私費で千部刷られたという。
わが国でも幻の名著となっていたが、1968年にようやく、世界的な要望のうちに再版された。限定復刊。
1927年に『精神分裂病』を著わした著者は、分裂病者の時間と空間における特殊な存在の形態、特異な世界への入口を模索しつづけていた。ベルクソン、フッサールの影響が色濃く影を落している本書はその延長線上にある。1933年、『生きられる時間』が生まれたときは、私費で千部刷らせたという。わが国でも幻の名著となっていたが、1968年ようやく、世界的な要望のうちに再版された。ミンコフスキーは、その序文のなかで次のように述べている。
出典: www.msz.co.jp
「われわれが今読者に提供する書物は、もとのテキストの再版であって、第二版(改訂版)ではない。それは余分の労苦を払うことを惜しんだからではない。他の動機があったからである。まず個人的な動機として、この労作は、言ってみればただ一つの魂をなして流れでたものであるということである。より一般的な動機としては、私は、やはり思うに、手応えのある程度には、現代思想において時代を画した、ということができると信じているからである。
出典: www.msz.co.jp
この著作の特徴は、現象学的・精神病理学的研究というその副題が示している。ふたつのものは、そこで密接に結合しあっている。アンリ・ベルクソンの影響をそこに見出すことは容易である。そこでは感情的接触の観念の代わりに、それよりはもっと広い、生命的接触の観念が立てられた。……現代の精神病理学における哲学的傾向性が出て来るのは、そこからほんの一歩である。哲学的と言われるこの流れが精神病理学において明らかにした与伴は、象徴的なものではなくて『事実』であるということである。」
出典: www.msz.co.jp
俺の書きたいものは、生きられる時間なんだよね。だから、ミンコフスキーの『生きられる時間』って本を知った時、猛烈に欲しくなった。
— お察しください (@st70521) 2014.10.24 03:08
ミンコフスキーの生きられる時間に影響を受けているので、御阿礼の子について考える時もそういう哲学の影響が出てしまうし、ベルクソン的解釈も必要になってしまい、小林秀雄か……ってなる
— お察しください (@st70521) 2015.12.10 23:25

出典: www.amazon.co.jp
レヴィナス『全体性と無限』
西欧哲学を支配する「全体性」の概念を拒否し、「全体性」にけっして包み込まれることのない「無限」を思考した、レヴィナス(1905―1995)の主著。
暴力の時代のただなかで、その超克の可能性を探りつづけた哲学的探求は、現象学の新たな展開を告げるものとなる。
![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)