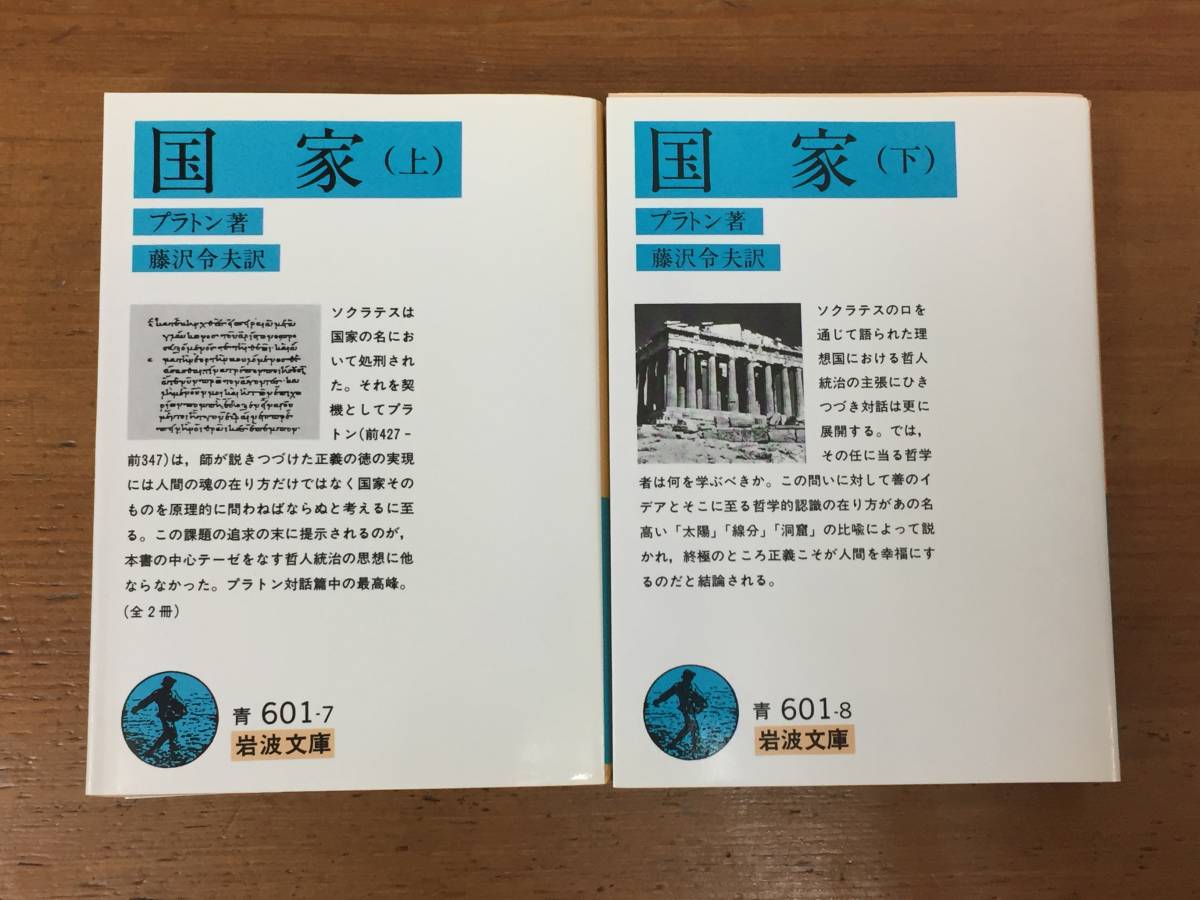
長年に渡り世界中で読み継がれている哲学や倫理学、心理学の名作をまとめました。古代ギリシアの哲学者プラトンの『国家』や、ドイツの思想家ニーチェの『道徳の系譜』など、各作品の基本情報や読者の感想をまとめています。哲学入門編にぴったりな本もまとめて紹介しています。
哲学など現代においては無用な営為だ、と考えるような人たちにも是非読んでもらいたい書物、それがこの『危機』書である。
出典: www.amazon.co.jp
フッサールが最終的に至った超越論的自我は、言うなれば生活世界を認識し妥当を形成する心理学的自我をも見つめ構成し、どこにも定在を持たぬような自我。言ってみれば究極的にはここから世界を把握する。この把握が他者のそれと重なり合うことで謂わば真理が生まれる。ことに生活世界に共握の可能性があることには必然性がある。これが自分の現象学理解だ。
出典: www.amazon.co.jp
彼の哲学は未だに色褪せていないし、その真摯な学問態度には胸を打たれさえもする。「暗い時代」を生きて現象学を伝えてくれたフッサールに畏敬の念を持ってこの本を読み終えた。
出典: www.amazon.co.jp
フッサールの『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』を再度最初から読み始めた。彼の問題関心を出来る限り彼の関心にそって理解する努力は、非常に骨が折れるが、実りも大きい。
— こてこて (@kyodatsu_kote) 2017.10.02 22:33
小松左京がフッサールの『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』を全文写本してたという話があるけど、現象学をどのようにフィクションに反映させてるんだろうか?
— 柊あすかい (@askai33) 2017.06.07 01:21

出典: www.amazon.co.jp
メルロ=ポンティ『知覚の現象学』
サルトルとならび戦後思想の根底に計り知れぬ影響をもたらした著者の記念碑的大著の全訳。
近代哲学の二つの代表的な立場、主知主義=観念論と経験主義=実在論の両者を、心理学・精神分析学の提供する資料の解釈を通じて内在的に批判するとともに、両義的存在としての「生きられる身体」の概念を回復し、身体=知覚野において具体的・人間的主体の再構築をめざす。
『知覚の現象学』はメルロ=ポンティの主著であり師フッサールの『論理学研究』とともに「現象学」の金字塔といえるでしょう。
出典: www.amazon.co.jp
メルロ=ポンティは『知覚の現象学』で、フッサールの「事象そのものへ」という理念を継承し、「知覚」がただ外部からの刺激を受け取るだけでなく「意味」や「価値」を付与し処理するさまを描いています。哲学で認識論や心体論を研究されている方はもちろん認知心理学や脳科学を専攻されている方にも示唆に富んだ作品といえるでしょう。
出典: www.amazon.co.jp
さて本作や法政大学出版局・中島訳のほかにみすず書房・竹内監訳が存在します。後者の方が原著のページが載っており、引用されることも多く原文の雰囲気をたたえているとは思いますが、日本語だけで読んだ場合前者の方が日本語として自然で読みやすいかと思います。また一巻本でかさ張らない(ただし腕は鍛えられます)ので「とりあえずメルロ=ポンティの代表作を読みたい」という方は法政大学出版版をおすすめします。
出典: www.amazon.co.jp
「日本人は怒ると微笑する。」(メルロ=ポンティ『知覚の現象学』p.313) これはw
— 黒葛原一樹 (@unnamable1897) 2017.08.28 16:57
訳は分からないけれどメルロ=ポンティの知覚の現象学という本を鷲田清一さんを知った流れでなんか面白そうじゃんと手に取って値段みたら8000円くらいしてヒッッてなった
— ごごの (@gogono05131) July 13, 2017
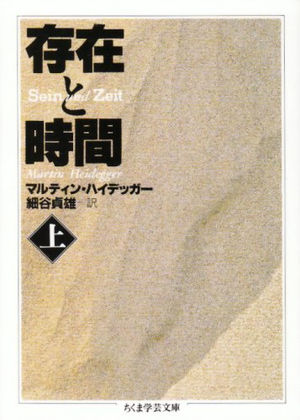
出典: www.amazon.co.jp
ハイデッガー『存在と時間』
1927年に刊行されるや、ドイツの哲学界に深刻な衝撃をもたらした、ハイデッガーの最初の主著。
《存在》の諸相をその統一的意味へさかのぼって解明すること、そして、存在者の《存在》を人間存在(=「現存在」)の根本的意味としての《時間》性から解釈することを主旨として、「現存在の準備的な基礎分析」と「現存在と時間性」の二編から構成する。上巻ではこの前者を収録した。
「現存在」の根本的な構成が「世界=内=存在」として提示され、「現存在」のうちに見いだされる「存在了解」を探求すべく、基礎的な問いが差し出される。
もう何年も前に買って、とっつきにくさに辟易して挫折したまんまになっていた。
その後永井均の「ウィトゲンシュタイン入門」を読み、木田元の「反哲学入門」を読み、ニーチェやキルケゴールを読んで、再び本書に挑戦しようという気になった。
で読んでみたら、ややこしい部分もあるが読めるのだ。
出典: www.amazon.co.jp
おそらく永井先生のおかげが一番大きいだろう。ウィトゲンシュタインとハイデガーが似ているとは思わないが、科学の多様性の誘惑を退けて自分の本質や限界に想念を沈めてみるという感覚は共通なのかもしれない。
出典: www.amazon.co.jp
小説等に比べると比較にならない程の時間はかかりますが、根本的な要点を理解した上で読むと非常に面白く、真に普遍的な存在を解明していくためには非常に優れた資料となる書物だと思います。まだ概観したような状態で上下とも深く読み込めていないのですが、何度か読み込んで更に理解していきたいと思います。
出典: www.amazon.co.jp
ハイデガーは難解をもって知られる哲学者です。主著は『存在と時間』で、「人間」という言葉を使わず、「現存在」で通すのです。この「言い方」(言い換え)の奇妙さ=うまさが、ハイデガー哲学を成功に導いた鍵です。 こう言い切る堀川哲さんの紹介=解釈は、ユニークですが、本筋をついています。
— 鷲田小彌太bot (@washida_bot) October 21, 2017
ハイデガー『存在と時間』入門(轟孝夫)を讀む。
— 禁煙先生 (@kinnensensei) October 22, 2017
「伝統的存在論は『何かが存在する』というとき、その存在者の現前を支えているこうした隠された地平を、それらが隠されているがゆえに見落としてしまい、何かが『ある』ということを、単純にそれが今、現前していることと同一視する」

出典: www.amazon.co.jp
アーレント『精神の生活』
人間の精神の営みは何のためにあるのか。
ナチスの蛮行のような巨悪は、人間が「考えない」ことにかかわって生まれるのではないのか。
生涯をかけて人間の自由と全体主義的独裁の問題を追究したハンナ・アーレントの遺著。
ヨーロッパ哲学の正統的な流れに含まれる危険な要素をえぐり出し、現代社会の「思考の欠如」の行く末を厳しく警告する。
『イェルサレムのアイヒマン』を通じて、「強い悪の意思」ではなくて「人間の凡庸さ」こそが巨大な蛮行を可能にしたのだ、と著者自身が痛感した、という。そして、その凡庸さは「考えないこと」によって可能になる、と思い至ったという。
出典: www.amazon.co.jp
そこから、ギリシア・ローマ以来、近代の哲学者たちの「思考」に関する考察を述べる。
ページごとに刺激・啓発を受けるので、少しずつ読み進んだ。しかし、けっして手放そうという気は起きなかった。
荘子の「胡蝶の夢」も登場し、著者の博識と洞察、思考過程、つまり哲学そのものが生活になっている姿が感動的である。
憧れをもって読んだ。
出典: www.amazon.co.jp
普段はまったく気に留めないようなことをあえて掘り下げて試る。すると非常に難解だったりする。でもそんな難解なこととの出会いって非常に大切なことかもしれない。もしかしてそれは難解じゃなくて感動だったのかも。
出典: www.amazon.co.jp
お、アーレント『精神の生活』第3部に迫っていこうという感じの本が出版されるそうですね.これ、すごいのでは
— けーじん (@keijin_) June 5, 2017
アーレント『カール・マルクスと西欧政治思想の伝統』を読み直していたら、やっぱりこの本面白いなぁと思った。その後に展開されるアイデアがここにギュッと凝縮されているような印象。『人間の条件』『革命について』『暴力について』『精神の生活』『カント講義』等の基本アイデアが既にここに!
— ばく (@kapibaku) October 9, 2012
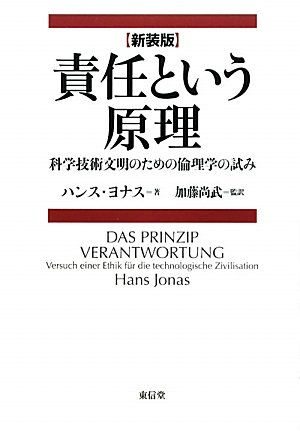
出典: www.amazon.co.jp
ヨナス『責任という原理』
今こそ全存在の未来を担う「責任という原理」へ。
「希望」とは、確実な裏書きもなしに、現在が未来へ向け振り出した約束手形だ。
そして「持続可能な開発」などの耳障りのいい決まり文句が示すように、人類はなお「希望という原理」に浸蝕されたままである。
未来への「責任」の強い自覚なしに推進される「希望」は、すなわち悪しき終末への道だ。
強権という前近代的な方途を超えて人類の英知を糾合するため、今こそ全存在に対する人類の歴史的責任を告知・論証した本書再読・熟読の時だ。
![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)