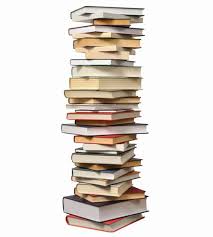
面白いだけでなく、読んだ後に何とも言えないような、煩悶ともいえる感覚を味わえる小説を集めてみました。「じゃ、いっちょ読んでみるか…」となっていただければ幸いですが、モヤモヤするのも事実なので、自己責任でどうぞ。別段ホラーでもないんですけどね。
『占拠された屋敷』(フリオ・コルタサル)
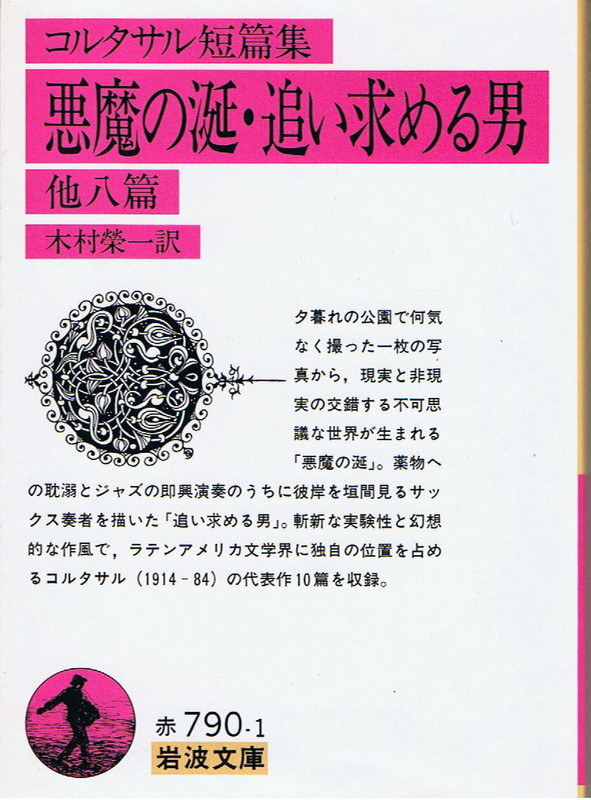
数名は楽に暮らせそうな広い屋敷。丈夫な樫の木材のドアでで前部分と奥部分が分かれており、中年の兄妹が二人きりで暮らしています。結婚はしておらず、土地代により、あくせく働くこともせず、家事が終わればお互い自分の好きなことをしていました。が、ある日異変が…屋敷の奥部分が何者かに「占拠される」のです。「占拠したもの」の正体、そもそも「占拠する」ということがどういうものなのか、最後まで説明はありません。しかし、兄妹は樫の木でできたドアの鍵を閉め、かんぬきまでかけ、二度と奥へは行きませんでした。10ページ足らずの作品の中、分かっているのは「兄妹の境遇」と「屋敷が何かに乗っ取られた」こと、そして「占拠された」かどうかは、「物音」で分かることくらいです。怖いというより戸惑いを覚える作品ですが、何度も読み返したくなるから不思議です。画像の短編集には他にもどこか非現実的な作品が収録されています。『悪魔の涎』『続いている公園』など、『世にも奇妙な物語』で映像化して欲しい(後者は無理かも)ほどです。
『少女架刑』(吉村昭)

女の子の死体を解剖する話、といっても猟奇ものではありません。語り手は死体ご本人。恐らく昭和の貧乏長屋で生まれ育った少女が16歳にして死亡し、大学病院に「標本」として売られる、というのが実情です。生前中々美少女だったようですが、皮膚も内臓もすべて、新鮮な標本としてとられます。一応感覚はあるようですが、痛みはないのか、淡々と自分が解剖されていくさまを語ります。淡々としすぎていて、逆に怖くないほどです。一方で、脳を失ってもまだ意識がある彼女は過去を回想したり、これからどうなるんだろうかと思ったり、職員たちの話を聞いていたり…静かな声で朗読しているかのような印象の文体で物語は進んでいきます。彼女は最終的にどうなるのか…?個人的には何とも言えない気持ちになりました。
『おしまいの日』(新井素子)

もともとこの作品はラジオドラマで知ったのですが、これまた精神に来る話です。「24時間戦えますか」の時代、異例の出世を果たしがため仕事づめの夫と、その心配をする妻。なまじ趣味がなく、子供もいない状態の中、妻は次第に心を病んでいく…この二人があと15年ほど遅く生まれていたなら、或いは…などと思い、「どうにかできないのか」と言いたくなりました。でも、文体がどこか優しげで、色々な意味で涙が出てきます。
![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)
